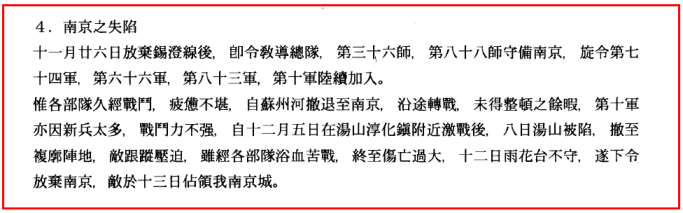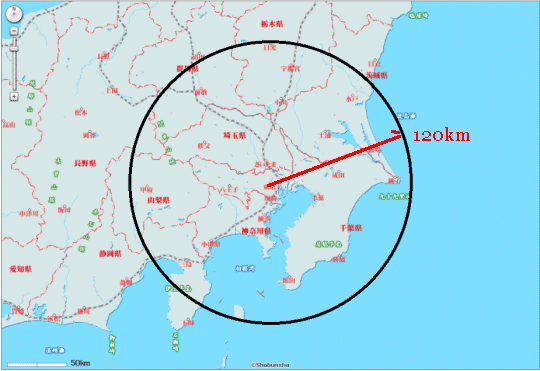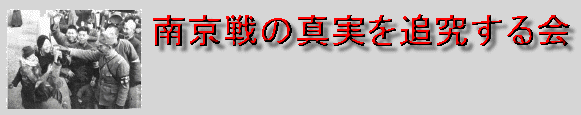筆・鹿島 明
このページでは、「何応欽上将の軍事報告」の中に「南京大虐殺」の記載がないことについて紹介します。
- 1.「南京事件の総括」からの引用
- これは、「南京事件の総括」(田中正明/著 小学館文庫)のpp.78-83で、「南京大虐殺」不存在の十五の論拠の一つとして詳細に論じられているので、同書から当該部分を抜き書きします。
= = = = = = = = = = = = = = 引 用 始 め = = = = = = = = = = = = = = = = =
「何応欽上将の軍事報告」
日本軍と戦った中国側の資料に南京事件はどう書かれているか。いま、筆者の手許に「中国現代史料叢書=対日抗戦」という著書がある。何応欽上将著、呉相湘編、第一版は一九四八年(民国三七年)一二月、第二版は一九六二年(民国五一年)六月発行、発行所は台北市文星書店。
いうまでもなく南京戦を戦ったのは、現在の北京政府でも中共軍でもない。台湾の中華民国政府、すなわち蒋政権の国民党政府であり、その軍隊である。当時の中華民国陸軍一級上将(大将)で、軍政部長(国防相)兼軍事委員会委員長何応欽将軍が、中華民国二六年(昭和十二年)の盧溝橋事件から、日本が敗北する中華民国三四年(昭和二十年)までの八年間にわたっておこなった軍事報告を一本にまとめたのが本著である。軍事報告というのは、日本の国会に相当する全国代表者会議に毎年報告して承認を得るもので、実に六八八ページにおよぶ浩瀚なもの。
その内容の豊富さと正確さは、序文にあるように「均為当時実況、官方史料、当以斯為最備」−すなわち、「当時の実況に基づいた公式史料であり、最も完備したもの」とみてよく、数百の統計や戦闘地図の入ったくわしいレポートであり、戦死者や負傷者の数も百人、十人単位といったこまかい数字までならべている。
軍編成や戦闘状況も精緻をきわめている。中国側の史料としてはこれ以上ない第一級の公式史料といえよう。
では、何応欽上将は南京戦争に対してどのような軍事報告を行なったか。 この報告は、首都南京の失陥の傷跡もいまだ生ま生ましい昭和十三年春、漢口で開催された臨時全国代表者大会で行われたもので、報告書の期間は、中華民国二六年(昭和十二年)の盧溝橋事件から同二七年(昭和十三年)二月までとなっている。
その軍事報告の目次のうち、
(一)自開戦起至南京失陥止作戦経過
というのがあり、八二ページに「南京之失陥」がある。「南京之失陥」自体は僅か六行で、非常に簡略に見えるが、損害人員等細部に関しては、このあとの、
(二)南京失陥後三月初旬止、作戦経過
でくわしく編成上のことや戦闘状況など細かい数字をならべて紹介しており、南京の部分だけをとくに外したわけではない。兵員の損害等については別に「我軍之状況」という項を設けてくわしく説明している。「南京之失陥」を翻訳すると次の通りである。
4.南京の失陥十一月二十六日、錫澄線を放棄したのち、すなわち教導総隊、第三十六師、第八十八師に南京の守備を命じると共に、これに第七十四軍、第六十六軍、第八十三軍、第十軍を参加せしめた。 思うにこれらの各部隊は戦闘久しきにおよび、疲労困憊に耐えず、蘇州河を撤退して南京に至ったが、途中転戦し、いまだ整頓の余暇も得ていない。とくに第十軍は新兵が多く、戦闘力に欠けるところがあった。十二月五日からの湯山、淳化鎮付近における激戦の後、八日遂に湯山陥落、やむなく複廓陣地を撤退したが、敵は攻撃の手をゆるめず急追し、各部隊は溢血苦戦を重ねた。しかるに死傷者相次ぎ、十二日最期の陣地である雨花台を守り切れず、遂に南京放棄を下命した。敵は十三日我が南京城を占領した。
ここには日本軍の暴虐も“南京虐殺”もどこにも出てこない。 なおこの報告書には戦闘ごとに詳細な統計が百数十点付録されているが、この中にも“南京虐殺”を匂わせるようなものは何もない。
・・・・・{中略}・・・・・ いずれにせよ、南京に万を越す大虐殺があったというような記録は中国側の第一級の公式史料である何応欽上将の軍事報告の中にさえその片鱗も見出せない。
中国問題の評論家であり、何応欽将軍とも昵懇の高木桂蔵氏は筆者に資料を提供くださり、次のように述べている。
「南京戦で万一、支那の軍民が何万も何十万も殺されていれば、そのことがこの報告書にのらないはずはない。ところが、日本軍による何十万もの虐殺があったなどということは、この『軍事報告』のどこにものっていない。これまで南京に関する多くの論争があったが、このような日本の交戦相手国の公式一級資料が、日本で出されなかったことは、むしろ不思議といってよかろう」まさに高木氏の言う通りである。東京裁判が公正な裁判ならば、当然、重要証拠史料として採用されたであろうし、また台湾の中華民国政府も、北京の中共政府も、当然、この重要史料を所持しているはずである(編注:日本の国立国会図書館に所蔵されている)。
ところが、日本が戦争にやぶれ、東京裁判がはじまると、南京事件に関する資料はガラリと変わる。二級、三級以下の資料価値ゼロの伝聞資料、政治的宣伝資料、憶測や創作に類するものまでが、次から次へと悪性腫瘍のように噴出し、そしてそこにもられた数字がひとり歩きし始めるのである。
引用元:「南京事件の総括」(田中正明/著 小学館文庫)pp.78-83= = = = = = = = = = = = = = 引 用 終 り = = = = = = = = = = = = = = = = =
- 2.原典の確認
さて、ここから先、すべきことは、田中正明氏が和訳した「南京之失陥」の原文である中文が、「中国現代史料叢書=対日抗戦」(何応欽上将/著、呉相湘/編、台北市文星書店/刊)の現物に実際に記載されているか、の確認であろう。
田中氏によれば、同書は「日本の国立国会図書館に所蔵されている」とのことなので、国立国会図書館において参照を試みたが、 筆者の調査時点(平成27年12月)では、同書の所蔵は東京館ではなく、関西館に移転していた。 そこで、東京館において参照の代理手続きをしたところ、まもなく回答があり、それによれば、中文は以下のようになっている、とのことであった。
(Source: p82, 何上将抗戦期間軍事報告 文星書店 1962, Taiwan)
確かに田中氏の記述のとおり、「南京之失陥」の本文はわずか六行に過ぎず。そこには「南京大虐殺」を伺わせる記載はない。
- 3.地名その他の確認
「錫澄線」については、「新『南京大虐殺』のまぼろし」(鈴木明/著)のp.214に説明がある、
同書によれば、国民党軍は「呉江市(太湖の東)から北に蘇州、常熟、福山を結ぶ防衛ラインを「呉福線(または第一ヒンデンブルク線)」と呼び、無錫(Wuxi太湖の北)から江陰に至る防衛ラインを「錫澄線(または第二ヒンデンブルク線)」と呼んで陣地を構築していたという。
また、日本側で江陰(Jiangyin)と呼んでいた地名を中国側では「澄江」と呼んでいたので、無錫−江陰間の防衛ラインを「錫澄線」と呼ぶとのこと(前出書p.217)。
南京市と「錫澄線」の間は約120kmであるから、東京都庁付近を南京城とすれば、「錫澄線」は銚子、富士、甲府、宇都宮の各市を同心円で結ぶくらいの距離であろう。
「湯山」(とうざん)と「淳化鎮」の位置は下記の「南京近傍略図」のとおりである。南京市の中山門付近から約12km、同じく東京都庁付近を南京城とすれば、江東区南砂町、足立区舎人公園、武蔵野市吉祥寺、大田区大森町を同心円で結ぶくらいの距離であろう。
日本軍は、12月5日に南京城から120km離れた防衛線を突破してのち、7日目は「最後の陣地」である雨花台を陥落させ、その翌日には偵察のための先遣隊を南京城内に侵入させている。
「虐殺派」の主張の一つに、上海から南京にかけての「江南地方」の各地で日本軍が「大虐殺」をしたというものがある。 しかし、これほど急速な部隊移動をしている途中で、そんな脇道にそれた行動をしている余裕があるだろうか。常識で考えても有り得ない。
また、別の見方をすれば、南京城の外側の「南京市指定区域」で日本軍が「大虐殺」をしたという「虐殺派」の主張も成立しない。 日本軍による南京城総攻撃は12月10日のことであるから、南京城付近の住民が退避・疎開を完了するまで、 上海戦が終結した11月半ばから数えれば、なお約1ヶ月、120km離れた防衛線を突破された11月26日から数えれば、なお2週間弱、 南京城の目と鼻の先の要地が陥落した12月5日から数えても、なお5日の余裕があったのである。 仮に徒歩であっても、4〜5日あれば移動できる距離を想像してみればよい。
更に、日本軍の進撃・包囲ルートは南京城の東と南からであるが、北と西はガラ空きである。 これは、まるで「戦いに巻き込まれるのがイヤなら、さっさとお逃げなさい」と言っているようなもの。 揚子江が南京城の西北を流れているけれども、小船で対岸に着くなり遡行すれば戦闘とは無縁の世界だったはず。 もしも、日本軍に南京城内の軍民皆殺しの意図があったなら、揚子江対岸の北と西からも包囲しないと理屈に合わない。
都庁付近で砲撃戦があっても、60km以上離れた小田原付近に滞在する人間にとっては他人事に近いはずである。 このことは、「空襲警報発令」から僅か数時間で大規模かつ広範囲に焼夷弾の雨を降らせた米空軍の日本本土都市攻撃の残虐性と比べれば、 住民に逃げる余裕を与えないという点において、いっそう鮮やかな対比をなすはずである。
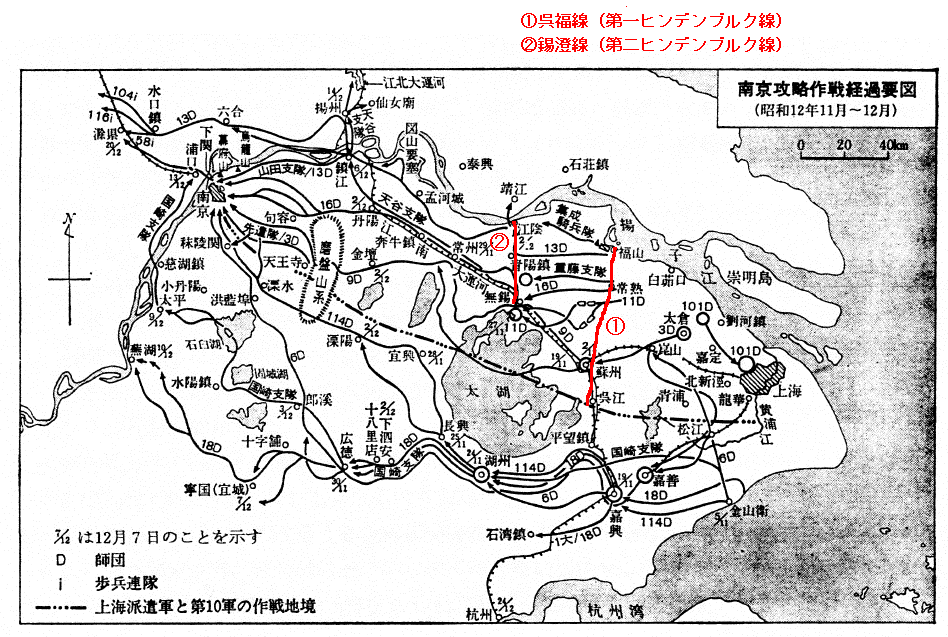
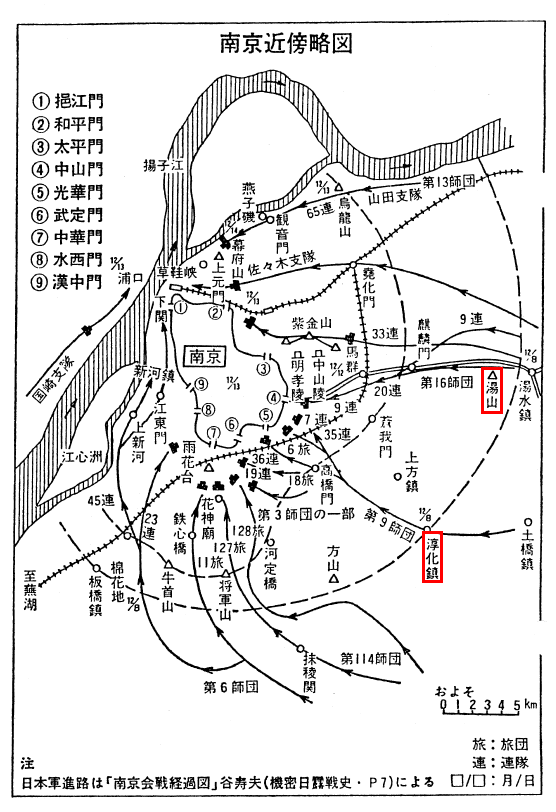
- 4.結論
上記、「何応欽上将の軍事報告」の中に「南京大虐殺」の記載がないという事実を覆すに足る新たな史料が発見されない限り、国民党政権の公式史料に「南京大虐殺」は登場しない。